浅子没後一〇〇年
成人を迎える方へ──
「九転十起生」からのメッセージ
はじめに
二〇一九年一月一四日。この日は広岡浅子が没してちょうど一〇〇年となる節目の時です。浅子の死から一〇〇年後の日本では「成人の日」ということで、全国でも多くの成人式を迎えた二十歳の若者が、未来に希望を馳せていることでしょう。
今回は、広岡浅子が残した言葉の中から、若者へと向けたメッセージをご紹介します。ちなみに、「九転十起生」とは浅子の座右の銘に由来する浅子のペンネームです。
「本気におやりなさい」
まずご紹介するのは一九一二(大正元)年、浅子が六四歳の時に「婦人の友」という雑誌に寄稿した文章の一節です。激動の時代であった「明治」から新たな元号「大正」へと変わり、新たな時代に女性がどのように生きるべきかを主題としたものです。
「絶えず自ら教育するということは、努めなければどんなに閑な豊かな境遇でもできないもので、十分の覚悟を以て努めさえすれば、またどういう境遇にあっても出来るものです。このようにまず始終自らを教育しつつ職業に従うなら、ままごとではなく本気におやりなさい。
(中略)
常に謙遜な真実の心をもって自分を省み、修養を怠らない人であったならば、その人のする仕事は小さくても大きく役立ちもし、またその周囲に何らかの感化を及ぼすでありましょう。そして大きな仕事であればなお、小さい隅々まで行き届いて、しっかりとした土台から積まれ、充実した内容をもって力ある大いなる貢献を致すのでありましょう。」
明治から大正に改まった当時、一つの時代が終わり新しい時代が始まるという感覚は、現在の我々よりも強いものがあったことでしょう。そんな新しい時代に日本はどうあるべきか、女性はどう生きるのか、ということを寄稿する中で、浅子は意外にも「実践せよ」「修養を怠るな」ということを強調しています。この「ままごとではなく本気におやりなさい」という言葉に続き、浅子はこう説きます。
商売をするならば、その道の玄人に負けない知識をもち、商店と競争して利益を挙げる覚悟をするがよい。貧民救済に働こうとならば、自ら汚い貧民窟に入り込んで、生活の有様を見てきて、始めて彼等を救う方針が立つのであります。職工を教育しようとならば、彼等の友として働いて、まず彼等の考うる所、求むる所を知ってから、導くべき道が見出されるのであります。
「本気にやる」。このことは、炭鉱事業を成功させるため、鉱夫たちが住んでいる炭鉱で生活を共にしたなど、浅子自身が実践し続けてきたことに他なりません。

「小事は大事を為す基をなす」
続いてご紹介するのは、浅子が日本女子大学校桜楓会の部会で語った言葉です。桜楓会とは日本女子大学校の第一回卒業式(一九〇四(明治三七)年)とともに発足した同窓生組織で、現在も活動を続けている伝統ある組織です。日本女子大学校の卒業生ではない浅子ですが、この桜楓会を外部からサポートする桜楓会補助団を結成して自ら幹事となり、同会の活動に積極的に関与していました。
話の内容としては、女子大学校を卒業後、特に家庭に入ってしまうと日本女子大学校の高等教育で得たものを十分に生かせずなかなか理想とする社会へとたどり着かない……という会員の声があったようで、それに対する浅子の言葉になります。
「人々が往々理想が実際に行われぬとして苦しむが、それは大なる間違いであります。(中略)幾分ずつなりとも、その現在の境遇よりもよりよく為さんと思うて、小さき所より改良し行くべきです。小さきところより順を追うて改め行けば、概して衝突はないものであります。
(中略)実に小事は大事を為す基をなすものである。而して己を屈して次第に理想に近づかんと欲する時、奮闘が起こりましょうが、その奮闘は決して苦痛ではなく、一つの楽しみであります。自分の理想が高ければ高い程、社会はつまらなくみえ、一層奮闘の度を強くしなくてはなりますまい。しかし奮闘の大なるだけ、それだけその人物を鍛錬します。高等教育を受けた皆さんは決して安きにつかず、また煩悶に終わらず、奮闘しては理想を現はし、理想を現はしてはさらに理想を高めて、永久進歩発達なさるよう希望いたします。」
いつも「日本の未来」や「女性の社会進出」など大局的な視点から語ることが多い浅子ですが、「理想の社会のならないことを嘆く」という風潮には一貫して批判的でした。なぜなら、理想とする社会を実現するためには小さなことから行動すべき、というのが浅子の具体的な考えだったからです。その小さな行動を達成するために「奮闘」が生まれ、その「奮闘」が、社会をより良い方向に発展させて遂には理想とする社会ができていく。それが浅子の信念とも言えるもので、これもまた、企業経営で培ったものかもしれません。
「九転び十起き」
浅子の座右の銘ともいえる「九転十起」。それが浅子自身の言葉として初めて出てくる新聞への寄稿文をご紹介します。
この前段で浅子は、当時の日本人とくに女性に古くから根付いている問題点として「他人の目や周囲の風評(小我)を気にして、自分が社会においてなすべきことや国がどうあるべきかなど(真我)を知ろうとしない」と指摘しています。それではその「真我」をどのように得られるのか? そこにあの言葉が登場するのです。
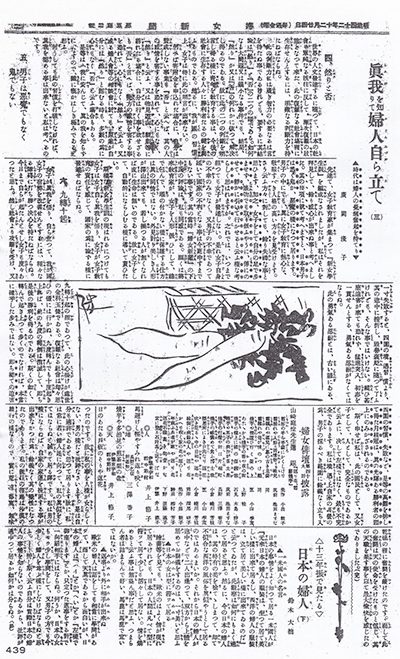
女子が真我を悟り、自ら立って、わが国の女子の宿弊を改善せんとするには、種々なる障害に打ち勝つ決心を持たねばならぬ。今日まで自らが起たんとせし女子も度々あったと思う。しかし社会より攻撃を受けまたちょっと失敗すると四囲の境遇習慣よりその途中に挫折し、毀誉褒貶に随ってしまうけれども、そんなことではいけない。たとえどんな迫害が来ても恐れず、猛進突入、初志を一貫せんとする、勇気ある忍耐がなくてはならぬ。
この勇気ある忍耐とは、古いことわざにある、九転び十起きの謂であって、この心がけが処世の金科玉条である。複雑なる社会はなかなか思いのままには行かぬ、九度転んでも十度起き上がれば、前の九度の転倒は消滅して、すなわち最後の勝利を得るのである。かくのごとくして転んで起き上がって歩くのでなければ、本当にしっかりした歩みではない。すなわちすべての迫害四囲の習慣、失敗など、これらの万難を排して得た月桂冠は、真の光輝ある勝利者の頭上にのみ、かざされるのである。
実業家として著名な存在となり、かつ日本女子大学校の設立にも大きく寄与し、周囲から「成功した女性」「立派な女性」と羨望や尊敬の眼差しを受ける立場となった浅子。そんな浅子ほどの人物でも「複雑な社会は思い通りにならぬ」と断じています。
思い通りになるから頑張るのではなく、思い通りにならない世の中だからこそ、自分の理想を決して諦めず、「九回転んでも十回起き上がる」。これが浅子の「九転十起」に込めた想いなのです。

終わりに
以上、浅子の言葉を三編紹介しました。百年経った現代の我々が読んでも、感じるところのある言葉ではないでしょうか。
後年、浅子に対してある若い女性が「なぜそんなに老いを感じさせず若々しいのか」を尋ねたところ、浅子はこう答えたそうです。その言葉をもって、本編の締めとさせていただきます。
(言葉は現代風に改めました)
「この問いには、『無限の希望』であるとお答えしましょう。(中略)どう熟考しても、私の希望が果たされる日はまだずっと先のことと感じます。しかしそれまでに自分が生きているかどうかを気にする暇もなく、いまもなお無限の希望に満ちて百年の計画を実行しようとしている、これが、私が老いを感じさせない大きな理由なのです。願わくは、我が国の女性が大いに覚醒してこれまでの弊害を改め、無限の希望に生き、老いを気にしないようになれば、必ずや我が国の内的革新である第二の維新は、きっと女性の手により達成される日は、そう遠いことではないと信じているのです。」






